写真>浪華写真倶楽部
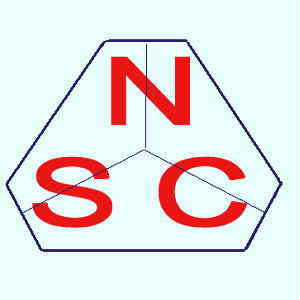
浪華写真倶楽部は、1904年(明治37)に設立され、現在も継続している歴史ある大阪の写真倶楽部です。時代の風潮に影響を受けながらも、大阪と
いう反骨・進取精神の息づく都市をベースに「キカイ道楽で贅を競う」雰囲気から芸術写真、新興写真、戦後のリアリズム的写真と、個人の画風とアマチュアリ
ズムを大切にしながら、その倶楽部史は日本の写真史の流れをよく見せてくれます。
1904(M.37)年1月9日(日露戦争開戦間近)、写真材料商桑田商会(桑田正三郎経営)の後援で大阪に設立されたアマチュア写真家団体。桑田
正三郎、石井吉之助により設立が発表された、日本で一番古い写真クラブ。初期の有力メンバーは横山錦渓、石井吉之助、米谷紅浪など。創立翌年から機関誌
「写真界」(M38−S3)を刊行。
昭和初期に実験的な写真表現で前衛写真をリード、多くの作家を輩出したが戦争で休会。戦後に再建され丹平、地壊社などと共に関西写壇を牽引してきた。(参照 写真辞典p347)
時代区分
初期は純粋なアマチュアリズムの中で自分たちなりの「芸術写真」を愉しみながら作成するような雰囲気のある活動、
明治末期から大正期にかけてはピクトリアリズム(絵画主義)を志向、 1921年(T.10)東京写真研究会初の関西での展覧会にて大きなショックを受け転換期となる。
昭和初期、新興写真運動の中心グループへと急変、そのモダニズム性を徹底させシュルレアリスム、アブストラクト的傾向を加えた前衛写真運動を繰り広げた。戦後、主観主義的写真の影響から、人間に目を向けた作品傾向へ移行していった。
会 則
1.本倶楽部は浪華写真倶楽部とし写真芸術に関する研究と会員相互の親睦を図るを以て目的とする。
2.本倶楽部は毎月撮影会及び例会を開催する。
毎年、審査員による成績表、(最高作品賞、次点賞、浪華賞、例会一席賞、浪展特選)がある。
『写真界』 月刊 1905年11月号〜1828年12月 桑田商会 1913年から写真界発行所 1914年から光画社 発行
浪華写真倶楽部の機関誌からのち一般読者向けの編集となる。

「会報」
 |
 |
日本写真史概説」参照 >TOPへ
| 1904 |
M.37 | 1月9日、浪華写真倶楽部創立 難波駅前明月楼にて設立発会式。 |
| 1906 | 第1回浪展開催(場所:大阪博物場→現貿易館) | |
| 1914 | T.3 | 会員 百名を突破 |
| 創立10周年記念祝賀会 | ||
| 1928 | S.3 | 2月 浪華写真倶楽部 創立25周年記念展 大阪 朝日会館 2/11-15 銀鈴社 の第1回展 大阪で開催。 |
| 1930 |
S.5 | 第19回浪展 特選 「進め」小石清 |
| 1930年代の会報表紙 | ||
| 1932 | 第21回浪展 大阪 三越 8月17-20日 東京 東京朝日新聞社 10月14-16日 | |
| 1934 | 30周年記念「会報」発行 30周年記念・第二十二回展覧会 大阪三越七階 8月25日〜8月27日 | |
| 1936 | S.11 | 第25回浪華写真倶楽部展覧会 8月22日−27日 大阪三越三階別館 |
| 1943 |
S.18 | 創立40周年記念第32回浪展(東京三越、大阪) 「福森白洋、安井仲治、桑田一郎三氏追悼号」発行 |
| 1948 |
戦後第一回目の浪展。在阪丹平、地壌社、大研、稚草社、浪華の5倶楽部合同展として大阪三越にて開催 |
|
| 1953 |
S.28 | 創立50周年 第38回浪展を単独で富士フィルムギャラリーで主催 |
| 1959 | 浪展 浪華写真倶楽部東京展 5月15-20日 小西六フォトギャラリー 7年ぶりの東京展 | |
| 1964 | 創立60周年記念写真集「浪」発行 | |
| 1967 | 第49回浪展中藤敦遺作展併催 大阪心斎橋 そごう2階ギャラリー 6月29日〜7月4日 後援全日本写真連盟関西支部 | |
| 1990 | 「日本のシュールレアリスム1925-1945」展 名古屋市美術館 10月10日〜11月25日 | |
| 1991 |
H.3 | 第70回浪展記念・浪華写真倶楽部写真集「浪華」発行 第70回浪展 会場 富士フォトサロン |
| 1993 | 第72回浪展 会場 富士フォトサロン | |
| 1994 |
(H.6) | 創立90周年記念浪展 会場/大阪展 京阪ギャラリー・オブ・アーツ・サイエンス 会期/平成6年12月9日〜21日 会場/奈良展 奈良市写真美術館 会期/平成7年1月5日〜2月12日 |
| 1995 | 浪華写真倶楽部の90年 奈良市写真美術館 期間1月5日→2月12日 | |
| 2005 |
(H17) | 3月5日 ホテルニューオータニで創立100周年記念祝賀会がひらかれた。 創立100周年記念 浪展 浪華写真倶楽部 大阪展2005年3月3日(木)〜3月8日(火) 会場/京阪百貨店守口店7階京阪ギャラリー 奈良展2005年9月2日(金)〜25日(月) 会場/奈良写真美術館 東京展 2005年11月19日〜12月11日 会場/東京都写真美術館 ■主催:浪華写真倶楽部創立100周年記念展実行委員会 |
| 2005 | 「写真はものの見方をどのようき変えたか2創造・回帰」展 東京都写真美術館に数点、倶楽部の写真家の作品掲載 | |
| 2005/7 | 『浪展-浪華写真倶楽部創立100周年記念』 青幻舎 出版 | |
| 2007 2/23-3/1 |
創立103周年 第81回 浪展 会場 富士フォトサロン | |
| 2009 1/30-2/5 |
H21 | 創立105周年 第82回 浪展 会場:富士フィルム フォトサロン(大阪) |
| 2010 11/26-12/2 |
創立106周年 第83回 浪展 会場:富士フィルムフォトサロン(大阪) | |
| 2012 5/4-5/10 |
明治37(1904)年創立「第84回浪展」 会場:富士フィルムフォトサロン大阪 |
|
| 2014 1/17-1/23 |
創立110周年記念「第85回浪展」 会場:富士フィルムフォトサロン大阪 1月17日(金)〜2014年1月23日(木) |
| Topへ |
| 青潮写真倶楽部(1921.5-) | |
| 「天弓会」 (1922- |
当時の浪華写真倶楽部の主要作家たちの集まり |
| 「銀鈴社」 (1928?-1930) |
米谷紅浪、梅坂鶯里、望月廬戸、安井仲治などによって結成。 |
| 「大阪光芸倶楽部」 (1936- |
入江泰吉 「光芸社」の常連客から研究会設立の要望により、「光芸倶楽部」を結成。
翌年、会員30名近くになる。関西では昭和5年ごろから5大クラブとよばれた、 |
| 「 銀影探光クラブ」 | 森脇、本庄主幹 |
| 「O.C.G.(オオサカ、カメラアイ、グループの略)」 | 小石清 指導 |
| 「芦屋カメラクラブ」(1930-) | 1930年、芦屋在住の写真家中山岩太、写真材料店主ハナヤ勘兵衛(本名、桑田和雄)、および写真愛好家の紅谷吉之助、高麗清治らによって結成。 |
| 「 丹平写真倶楽部」 (1930ー |
心斎橋筋 丹平薬局写真材料部内に上田備山、安井仲治を中心に設立. 浪華写真倶楽部とは兄弟関係と言われる。両方の倶楽部に参加していた会員が多かったため。 .写真集「光」1940年刊行 ・椎原治(1905-1974)・佐保山堯海(1907-1990)・手塚粲(ゆたか) 棚橋紫水(1906-1991) ●「月刊大阪人」56号(2002年10月) 特集「昭和の前衛写真、丹平寫眞倶楽部」 *図表あり 目次 モダン都市・大阪が生んだ私芸術、再現「丹平ハウス」、幻の写真家「手塚眞」、本邦初公開!丹平の映画、大阪写真史、安井仲治と「丹平写真倶楽部、丹平の作家たち、証言丹平写真倶楽部、写真集「光」、ほか |
| 「地壊社」 | 安井仲治、 上田備山らの |
| 「大研」 | |
| 「シュピーゲル写真協会」 | 1953年、棚橋紫水が設立 佐保山堯海 |
| 「アバンギャルド造影集団 」 (1937〜 |
樽井芳雄の呼びかけで花和銀吾、平井輝七、本庄光郎らによって設立 シュールレアリズムの追求 |
| 「稚草社」(1932- | 田中幸太郎 |
・関西以外の写真会
| 新興写真研究会 | 渡辺義雄、掘野正雄 |
| 米子写友会 | 植田正治 |
人々はどのように写真と出会い、どのように写真ととりくんだか、1930年代という時代の中で |
Topへ |
| ヤスイ,ナカジ 安井仲治 (1903-1942) |
大阪平野町(現中央区)生まれ。明星商業学校卒業。家業の安井洋紙店に勤める。 1922年入会 リアリズムを基盤としながらも、新興写真の新しい手法を積極的に取り入れ、人物、風景、構成などあらゆる分野に独創性豊かな作品を発表。卓越した指導力。 戦前の日本写真界を代表する作家。丹平写真倶楽部にも参加。ドキュメンタリからシュルレアリスムまで手がけた。生涯写真の可能性を追求し続けた。人望あ り。自己の魂を磨き上げる一つの表現行為としての全く独自な作風を追求したアマチュアリズムの鏡であった。 代表作「彷徨えるユダヤ人」「山根曲馬団」「水」「犬」 『安井仲治写真作品集』限定50部非賣品(上田備山(編纂兼發行者)1942年(S17年) 講演「写真の発達とその芸術的諸相」1941年(『日本写真全集 ; 3 近代写真の群像/ 小学館 , 1986に収録) 追悼安井仲治 安井節子、安井仲雄、聞き手松本徳彦(『日本写真全集; 3 近代写真の群像 月報/ 小学館 , 1986) 『仲治への旅』森山大道 『安井仲治写真集Nakaji Yasui Photograppher 1903-1942 』 発行 共同通信 2004/11 『安井仲治写真作品集』 安井仲治著. [複製版]. 国書刊行会, 2005. (日本写真史の至宝)監修 飯沢耕太郎・金子隆一 秩入り 「近代大阪の人物誌⑦安井仲治と小野十三郎」寺田操「月刊大阪人」 |
| コイシ,キヨシ 小石 清 (1908−1957) |
3月26日大阪生まれ。1922年浅沼商会大阪支店技術部に入社。写真技術を学ぶ。 1929年S.3年入会 鋭敏な感覚と抜群のテクニックで戦前の実験的な写真表現をリードした。 1931年第2回国際広告写真展(朝日新聞社)で「クラブ石鹸」が一等賞 第6回日本写真美術展で特選 代表作「泥酔夢・疲労感」『初夏神経』 連作「半世界」(従軍写真家として渡った中国で現地撮影した写真に基づく連作。平和的な日常生活の中に忍び寄る死(戦争)の匂いを漂わせた。 1933写真集 『初夏神経』37,5X20cm総50p写真図版10枚(シング板表紙に鉄線コイルによるスパイラル綴じ)を浪華写真倶楽部から刊行。発行 丸善大阪支社 (東京都写真美術館図書室にてオリジナル閲覧可) 著作: 『撮影・作画の新技法』(玄光社)1936 『初夏神経 = Early summer nerves』小石清著. [複製版]. 国書刊行会, 2005.6 (日本写真史の至宝) 監修:飯沢耕太郎、金子隆一 主要展覧会 ・小石清作品展(小西六フォトギャラリー、東京、1959年8月)開催1977年 ・小石清と浪華写真倶楽部展 会期・会場: 1988年8月12日-31日, 西武百貨店池袋店6階ザ・コンテンポラリー・アートギャラリー 参考文献:小石清「初夏神経」については『写真集の愉しみ』飯沢耕太郎 p21〜30 小石清と前衛写真(日本の写真家・第15巻)/岩波書店/1999年 |
| ハナワギンゴ 花和銀吾 (1889ー1957) |
東京生まれ。府立一中、一高、1917東京帝国大学法学部卒業。大阪住友倉庫入社。幹部候補として入社、エリートコースを歩んだ人。リベラリスト。のち大阪府立商品陳列所所長。 1928年S.4年入会 語学堪能 博学 反戦思想、前衛美術の論理的指導 代表作「情慾的な風景」「複雑なる想像」 アバンギャルド・造影集団の結成に参加。 |
|
福森白洋 (1887-1942) |
1920年入会戦前の浪華の中核的存在 代表作「麓の村」「難波橋」「静物」など |
| ウメサカ,オウリ 梅阪鶯里 (1900-65) |
大阪府生まれ。明星中学卒業後、実家の株式仲買業の世界に。 1920年入会20年、30年代メンバーとして活躍。ゴム印画法を得意とし、純日本的な作画法であるが清新で格調の高い作品を残している。27年安井仲 治、らと「銀鈴社」を結成。戦後は、関西アマチュア写真界の指導的存在として活躍した。「法隆寺 聖観音立像」(撮影1929) 2000年「日本におけ る文化財写真の系譜」東京都写真美術館にて展示された。 天弓会メンバー |
| ヨネタニ,コウロウ 米谷紅浪 |
1907年(M40)入会 ゴム印画の名手 写壇今昔物語 代表作「人馬絡繹」、東京写真研究会の会員でもあった |
| ヒライ,テルシチ 平井輝七 (1900−1970) |
12月5日大阪生まれ。実家の貴金属店を継ぐ。アブストラクトの作品に終始し、鋭い着想の作品を残した。 1937入会 戦後も評議員をつとめる。また丹平写真倶楽部の主要メンバーでもあった。同時にアバンギャルド・造影集団の結成に参加。シュルレアリスムに傾倒。様々なオブジェを構成し、コラージュ、着色などの技法を用いて超現実世界を創作。アブストラクトの作品に終始し、穏健な人柄に似合わなぬ鋭い着想は幾多の名作を残した。 代表作「月の夢想」「顔」1935-1938年頃「秋」「額」「モード」 |
| ウエダ,ビザン 上田備山 (1902ー1984) |
本名 孝。東京生まれ。大阪三越が写場開設に際して、写真技術師として迎えられ来阪、浪華写真倶楽部を経て、昭和4年安井仲治と丹平写真倶楽部も設立。幾多の後輩を育て上げた。 小石清を指導 代表作「超特急」「地下鉄工事現場風景」など |
| 浅野洋一 | 古道具屋に生まれる。小石清に師事 代表作「光の生殖」1938 大阪カメラアイグループ会員 |
| 森脇英一 | 大阪カメラアイグループ会員。 代表作 |
| 田中正親 | 1935年入会 代表作 |
| 小林鳴村 | 本名:彦次。学習院から京大を出、大阪住友に入社。大阪陸上競技協会会長、近畿陸協の副会長。兵庫県鳴尾村に住んだので鳴村と号した、洒落た命名をした。 代表作「レイノズルの砲丸」「煙中作業」「エレクトロン」 |
| 村田米太郎 (1907−43?) |
代表作 |
| 服部義文 | 代表作「伝説(神々)」 アヴァンギャルド・造影集団にも参加。前衛的な表現を展開、その後、現実の被写体に迫る作風へ |
| 矢野敏延 | 代表作 シュールレアリスムに傾倒。 大阪カメラアイグループ会員 |
| サカタ、ミノル 坂田稔(1902-1974) |
愛
知生まれ。名古屋工業専門学校卒後、1926年から毎日新聞大阪本社に勤務。大阪在住時に「浪華写真倶楽部」に所属し、「新興写真」に影響を受けた表現で
同倶楽部の中堅として活動。1934年に名古屋に移住し、全国でも屈指の前衛写真の論客とも目されるようになる。1939年にナゴヤ・フォトアヴァンガル
ドを結成する。1941年『造形写真』を刊行。日本報道写真協会東海支部長。海外宣伝報道要員として徴用を受け、1941年よりジャワ派遣。前衛写真の挫
折をとおして民俗学へ接近した。 2003年名古屋市美術館にて写真展 |
| 戦後 現代 |
| 中藤 敦 | |
| ホンジョウ,コウロウ 本庄 光郎 (1907-1995) |
1936年入会。浪華と丹平写真倶楽部に属す。37年に「アバンギャルド・造影集団」の結成に参加。1956年「日本主観主義写真連盟に参加。シュールリアリズムの作品などを多数発表。 代表作 「夢の再生装置」「光る曲線」、「生ー意識の流れ」 |
| ツダ,ヨウホ 津田 洋保 (1923- |
奈良県生まれ。日本大学芸術学部映画学科から学徒出陣。1949年入会,52年はなや光画荘創立。 代表作写真集「木の色、風の音」「四季百樹の詩」他多数 現浪華写真倶楽部代表、 詳しくは<http://www.yo.rim.or.jp/‾t_yoho/index.html>へ |
| 関岡 昭介 (1928- ) |
1958年入会。 日本写真協会個展として73〜92年、「光景」「白い抒情」「気になる光景」 「大阪環状線−駅からの眺め−」「泥の河−大阪連河系−」「海風前線」 「metal scape」「大阪まんだら」などを開催。 |
| 高田 誠三 (1928- |
大阪市生まれ。大阪府立大卒。 1949年入会 元大阪芸術大学写真学科教授、 日本写真芸術学会 80年第8回写真芸術国際ビエンナーレで5大陸5作家に選ばれる。 写真集「彩々流転」 「暗室の特殊技法」朝日ソノラマ 1977 |
| 中森三彌 (1907-2002) |
1940年入会 大阪生まれ。1922年大阪光芸倶楽部へ入会。小石清の指導を受ける。 日本写真協会功労賞 「京の風物」、「花ごのみ」 |
| 中山登 | |
| 荻野正夫 | 各賞受賞 |
| 岡本 美和子 | 1929年満州生まれ。1955年大阪府立職業写真科修了。岡本美知子写真事務所、朝日カルチャーセンター講師。 全日本写真連盟理事、全日本女性写真コンテスト審査委員長、日本写真作家協会(JPA)会員 |
| 安藤 正夫 | 1938年入会 |
| 藤波 一成 | 1959年入会 |
| 中藤 譲 (1931-2006.4) |
1953年入会 1968年アサヒペンタックス日本の祭典フォトコンテスト金賞受賞 個展「佐渡」「河内飛鳥」「河内ふるさと」「葛城の辺」など |
| 関連人物・会社 |
ウジェーヌ・アジェ(1857-1927)Jean Eugene Auguste Atget 日本では 1933年『光画』2巻1号に伊奈信男の紹介文と共に初めて紹介された。(イウジェーヌ・アジエについてベレニス・アボットの文章)戦前の日本の写真界に 大きな影響を与えた「独逸国際移動写真展」(1932)にも数点のアジェの写真が展示されていた。幼くして孤児となり、神学校へ通ったが学業途中で働く。 演劇活動の挫折の後、写真を撮る。近代写真の先駆者とされる。マン・レイなどシュールレアリストにより「現実を超越した詩的普遍の世界」と評価される。 『回顧展』淡交社1998より
ハナヤ勘兵衛(1903ー1991) 芦屋カメラクラブ
中山岩太(ナカヤマイワタ)
近江写真用品・・・・同社は1915年に創業、感光材料、カメラ、写真用品、電子映像関連などを扱う卸業者の大手。株式会社浅沼商会、株式会社樫村、美鈴
産業株式会社と並び、富士写真フイルム株式会社の大手4特約店(いわゆる4特)の1つに数えられていた。写真用品ではHANZA(ハンザ)のブランドでも
知られる。2004年新会社「富士フイルムイメージング株式会社」(10月1日)に営業譲渡をした。
浪華写真倶楽部の会報を発行していた。
| 用字用語 |
チョロスナ 木村伊兵衛などのスナップ写真全般を評して、関西人特有のスラング
ピクトリアリズム
ピグメント印画法(pigment Print) 重クロム酸塩の感光性を利用して、銀の濃淡を顔料(ピグメント)に置き換える技法の総称。木炭画やコンテ画を思わせる絵画的マチエールが得られる。
新興写真....リアルフォト 新興美術 当時一般に用いられた用語で、今日前衛芸術と呼ばれる、既存の美術の制度に対立する先鋭な芸術運動。
ブロムオイル
19世紀末から20世紀初頭にかけてピクトリアル(絵画的)写真が全盛だった頃の古典的写真プリント技法
シルバープリント
前衛写真主流
新技法写真
アブストレー
シュール
| 関連リンク | Topへ |
写真関係美術館
・横浜美術館
・まぼろしのつくば写真美術館
・東京都写真美術館
・JCIIライブラリー(日本カメラ博物館)
・彩都メディア図書館
・芦屋市立美術博物館 中山岩太、ハナヤ勘兵衛と芦屋カメラクラブの写真を所蔵。
・清里フォトアートミュージアム
美術館検索リンク
・東京アートビート
エキサイトイズム
インターネットミュージアム
インターネットカフェ
文化遺産オンライン
ニュージアムぐるっとパス関西2005
関連写真展
小石清写真展 1985 ツァイト・フォト・サロン
小石清と浪華写真倶楽部展 1988
安井仲治写真展 1987 兵庫県立近代美術館
| 参考資料 |
●浪華写真倶楽部発行刊行物
・『浪展 浪華写真倶楽部創立100周年記念 1904-2004』浪華写真倶楽部編集 青幻舎 2005.7
・ 『 浪展 : 浪華写真倶楽部創立90周年記念』[浪華写真倶楽部] , 1994 , 42枚.
・『浪華 : 第70回浪展記念写真集』 浪華写真倶楽部 , 1991 , 147p.; 記念写真集「浪華」出版委員会
巻末収録:浪華写真倶楽部沿革史:p121〜138
・『 浪 : Selected Works of NANIWA SHASHIN CLUB 60th anniversary 』 浪華写真倶楽部
, 1966 , 122p.
巻末:創立60周年記念回顧座談会
「会報」 創刊1955年(S.30)会報復刊第一号発行 (写真事典より)
詳しくは米谷紅浪著「写壇今昔物語」田中正親著「今昔物語」藤波一成「私説浪華写真倶楽部史」など参考
会報 30周年記念号 1934 January
会報 福森白洋、安井仲治、桑田一郎三氏追悼号 1943年6月 S.18年
会報3号 小石清、花和銀吾追悼号 1957.4-12 S.33年3月発行
●主な参考文献 & URL
・『モダニズムの光跡 恩地孝四郎・椎原治・瑛九』 東京国立近代美術館 1997
・「写真:浪華写真倶楽部と夫弓会」 p61-80 『日本写真全集2巻 芸術写真の系譜』小学館 1986/11
・「解説 浪華写真倶楽部と作家たち/木村康夫」 p155-157『日本写真全集2巻 芸術写真の系譜』小学館 1986/11
・「小石清と浪華写真倶楽部」 p41-70『日本写真全集3巻 近代写真の系譜』小学館 1986/03
・「戦前の浪華、丹平写真倶楽部/本庄光郎」p4-5 『日本写真全集3巻 近代写真の系譜』小学館 1986/03
・『日本のシュールレアリスム 1925-1945図録』名古屋市美術館1990/10/10-11/25
・「関西アマチュア写真の系譜ー」『日本列島写真人評伝』/岡井輝毅 日本写真企画 1992
・
新興写真の時代第3回〜浪華写真倶楽部〜 2.基調講演「小石清と浪華写真倶楽部/中島徳博(兵庫県立近代美術館)」3.回想座談会「浪華写真倶楽部の作
家たち/高田誠三・津田洋・中森三爾」 (日本写真芸術学会関西シンポジウム1997/11/15ビジュアルアーツ専門学校於いて」『日本写真芸術学会
誌』 6巻2号 1997
・『小石清と前衛写真ー1930年代 写真家達の冒険と創造』」 日本の写真家 15 岩波書店 1999
・ 『日本写真史を歩く』 天才・仲治と山根曲馬団 飯沢耕太郎著 ちくま学芸文庫 1999
・「東京写真研究会」と「浪華写真倶楽部」p33-43 飯沢耕太郎著
『「芸術写真」とその時代』筑摩書房 1986
・「関西にも起こる近代化の波:小石清、安井仲治らの活躍」 p.42-48 『昭和写真五十年史』伊奈信男 S53 朝日新聞社
・「東京写真研究会と浪華写真倶楽部」p33-50『芸術写真とその時代』飯沢耕太郎著 筑摩書房 1986
『小石清と浪華写真倶楽部』」展図録 西武百貨店ザ・コンテンポラリー・アートギャラリー 1988
浪華写真倶楽部会報 第10号(昭和39−41年)中藤敦氏追悼「浪」出版記念号 1967
浪華写真倶楽部会報 第3号 小石清、花和銀吾追悼号 1957.4-12 (S.33.3発行)
浪華会報 復刊 1955 1−2
福森白洋、安井仲治、桑田一郎三氏追悼号 会報 1943.6
個人
『安井仲治 モダニズムを駆け抜けた天才写真家』(新潮社フォトミュゼシリーズ、1600円)
雑誌『デジャ・ヴュ』第12号(河出書房新社、1993年)、「安井仲治と1930年代」特集号。「流氓ユダヤ」と並ぶ連作「山根曲馬団」を中心に、良質な図版で作品を紹介。
『安井仲治展図録』(西武美術館、1987年)
全関西写壇五十年史 同編集委員会 1976年
全関西写壇史Ⅱ 60年のあゆみ 全日本写真連盟関西本部
月刊誌「大阪人」近代大阪の人物誌 安井仲治と小野十三郎
【日本の写真】
『日本写真家事典』東京都写真美術館 執筆 2000年 /2800円
飯沢耕太郎他『日本写真史概説』 岩波書店
飯沢耕太郎 『戦後写真史ノート』 中公新書
1993
同 『「芸術写真」とその時代』筑摩書房
同 『写真に帰れ 「光画」の時代』 平凡社
同 『私写真論』 筑摩書房
日本現代写真史1945→95 日本写真会協会編 平凡社 2000年
『写真、「芸術」との界面に:写真史1910年代-70年代』光田由里著 青弓社 2006 第7章 安井仲治−リアルさの前衛
【現代の写真】
同 『割レタ鏡タチノ国デ 日本の世紀末写真』
毎日新聞社
日本写真の最前線をレポート
URL
PDF「前衛写真家たちのモダン都市」美術都市大阪再発見−失われた都市の記憶を求めて 菅谷富夫(大阪市立近代美術館建設準備室学芸員)
東京総合写真専門学校(Tokyo college of photography